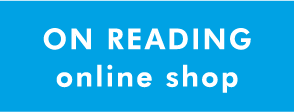2021-01
木村和平 写真展『あたらしい窓』

木村和平 写真展『あたらしい窓』
2021年2月11日(木)~2月28日(日)
※2月23日(火祝)は営業、24日(水)は振替休日
ファッション・フォトやアーティスト写真、映画のビジュアルなど、多岐にわたり活躍中の写真家、木村和平による写真集『あたらしい窓』(赤々舎)の刊行にあわせ、写真展を開催します。
——
近い存在であるはずのひとが、動物が、風景が、ふいに遠く感じることがある。それは寂しさや不確かさ、そして触れがたさとなって、短い風のように目の前に現れる。いくら被写体とカメラの距離が近くても、ひとがこちらに笑いかけていても、遠いときはとことん遠い。間に窓があるみたいに、見えるのに触れない。
写真はそれらを静かに、そして鮮明に提示してくれるものだが、理解につながるかは別の話だ。わからないことをわからないままにできるとき、私はとても落ち着いている。
これはなにも暗い話ではない。もちろん悲しくもあるけれど、親愛のなかにある距離を、どこか肱しく思う。
私は四六時中カメラを持ち歩くわけではないし、“撮るぞ”と意気込んで出かけることも少ない。1枚も撮らない日のほうが多いほどだろう。
これらの写真のほとんどが、2018年までに撮影したものだ。2019年の途中から、写真を撮る機会が減った。撮れなかったし、撮らなかった。単純に撮る気持ちになれなかったり、撮ってる場合じゃなかったり、ひととの関係に写真が異物に感じることがあったりと、様々な理由が考えられるが、いずれにしても私は、写真を撮らなかっ た日のことを肯定したいと思う。カメラじゃ遅すぎるときもあるのだから。
と、写真が身近なものではないようなことを書いてしまったものの、私は写真がないと全身の関節が外れて消えてしまう!
自分が写真でやりたいことはなんだろうか。常にアンテナを張り巡らせ瞬間を切り抜くことや、求める画のために場を作り込むことはしていない。はたまた、まだ誰も扱っていない新しい表現に注力しているわけでもないだろう。
日友の生活のなかでふと遭遇した、避けては通れない状況―― 相手との意思疎通、 すすまない時間、浮動する影、あるいは固定された光 ――に反応し、いつも「ちょっと失礼しますね」だとか心で唱えながら 、しつこく眺めて写真を撮る。生活の記録… といったものとはまた違うのだ。
幼い頃の体験や、いまも進んでいる生活に私はおおきな関心と執着がある。前者は独自のアルバムであり、後者は他の誰でもなく、自ら選んで作っていくものだ。住む 場所、食事、服装、そして関わる人々までも、自分で決めていい。知らない駅で降りてもいいし、猫と踊ったって構わない。
数々の体験と選択が、誰とも似つかないひとを形成していく。それぞれにオリジナルのエピソードがあり、その手触りが宿っている服や映画、そして音楽に感銘を受けてきた。それらはごく個人的なものごとを出発点にしながら、受け取るひとが自分のことのように思えるしなやかさと、そこから未知の眺めへとひらいていく豊かさを併せ持っている。私はそれを、写真でやりたい。
木村和平
——
木村和平
1993年、福島県いわき市生まれ。東京都在住。2018 第19回写真 1_WALL 審査員奨励賞 (姫野希美選)、2020 IMA next ♯6 グランプリ。主な写真集に『袖幕』『灯台』(aptp)など。





【展示後記】
木村さんの展覧会は、2019年の『灯台』展から2年ぶり。新作の写真集『あたらしい窓』の刊行記念展示でした。
今回の展示では、L判ほどのサイズのプリントがたっぷりと余白をとって額装されています。
そのため、鑑賞者は自分のからだを作品(被写体)へと積極的に近づけてみることになります。
“遠く”にあるように見えた写真は、そうやって覗き込むように見ることで、今度は親密さを感じることになります。
寂しいような、懐かしいような、暖かいような。「ここに写っているものは、もしかするといつか自分が見た光景だったのかもしれない…。」たとえば、そんなふうに。
木村さんと被写体との距離、今ここで見ている自分と被写体との距離。それがふと重なる瞬間、ともいえるかもしれません。
もう一つ。先日、金沢21世紀美術館で見たミヒャエル・ボレマンスとマーク・マンダースの二人展『Double Silence』の音声解説の一部をご紹介します。
「実際にそこにあるものが写真に写されると、とたんにそのものに対してよそよそしさを感じてしまいます。そこには実際にそこにあるものとイメージとしてのモノのあいだに大きさのブレが作用しているのではないかと彼(マーク・マンダース)は考えました。88%を境に、それよりも小さいとモノは現実から離れてミニチュアとして存在します。大きいと現実との区別がつかなくなってしまう。つまり88%がモノとイメージのあいだにあるよそよそしさの臨界点だと彼は考えているのです。」
私は、この言葉を聞きながら木村さんの写真をおもっていました。今回のプリントは現実と比べるまでもなく小さいのですが、近くで見るととても臨場感があります。だから尚のこと、河原でサッカーをしている少年たちも、ほの暗いホテルの一室の椅子もミニチュアのようです。そしてその、手のひらに収まるような世界を覗き込んでいるという鑑賞方法が、この作品たちを繊細な、宝物のように見せているのかもしれないと思いました。
2年前の『灯台』展では、会場を真っ暗にしたなかに、白黒の写真が少し低い位置に、ぼうっと浮かび上がるように展示されていました。
あの時も、鑑賞者は作品と向き合うために、からだを動かさなければいけなかったのを覚えています。
木村さんはいつも、写真集とも違う、展覧会ならではの鑑賞体験を見せてくれます。
だからまたこれからも、彼の展示が見たいと思うのです。
川原真由美「山とあめ玉と絵具箱」本屋を巡る、原画の小さな旅

川原真由美「山とあめ玉と絵具箱」本屋を巡る、原画の小さな旅
2021年1月27日(水)~2月15日(月)
高山なおみさんの著作『日々ごはん』『ロシア日記』『ウズベキスタン日記』の装画や、雑誌のイラストなどを数多く手がけ、また『十八番リレー』(高山なおみ)、『旬を楽しむ 日めくり七十二候』(白井明大)などの共著もあるイラストレーター・川原真由美による、10年以上にわたり親しむ“山”の魅力をぎゅっととじ込めた、瑞々しい、はじめての単著『山とあめ玉と絵具箱』(リトルモア)の刊行を記念して原画展を開催します。
川原真由美(かわはら・まゆみ)
1965年兵庫県生まれ、東京在住。東京藝術大学美術学部デザイン科卒業後、広告制作会社サン・アドでデザイナーの仕事を経て、2000年に独立。書籍・雑誌・広告を中心にイラストレーション、グラフィックデザインに携わりながら、作品を制作。40歳を過ぎて山に登り始め、山岳雑誌などに画文を寄稿。2010年より女子美術大学非常勤講師。共著に『ひとりがけの椅子』(文・青木美詠子 私家本)、『あたまの底のさびしい歌』(著・宮沢賢治 港の人)、『十八番リレー』(著・高山なおみ NHK出版)、『旬を楽しむ 日めくり七十二候』(著・白井明大 文春文庫)など。